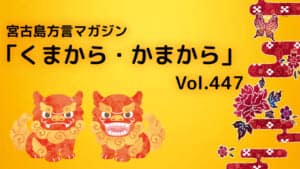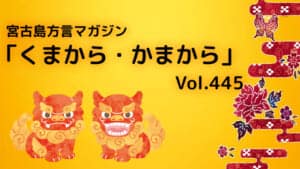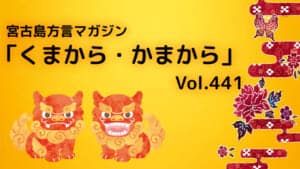こんにちは〜。
10月になりましたね〜。季節の変わり目ですが、がんづぅかり うらまずなー(お元気ですか)?
vol.397お届けです。お楽しみくださいね〜。
上野野原の十五夜行事『マストリャー』
松谷初美(下地・高千穂出身)
昨日は十五夜。宮古は夕方から雲がかかり、月は見られないかと思っていたら夜9時を過ぎた頃から、雲が切れ、サラーっと(はっきりと)見えてきた。?昨日は宮古の各地で十五夜の行事が行われた。
その中のひとつ、上野の野原で行われている五穀豊穣を祈る十五夜行事「マストリャー」を初めて見てきた。
会場の公民館はきれいに掃除がされ、入口のソテツで作られた門には「十五夜マストリャー」の横幕が掲げられている。
公民館敷地内に「マストリャー」についての説明看板があり、それによると野原の「マストリャー」は約300年ほど前から行われている行事で「マストリャー」の語源は「昔は穀物などで税を納めていたことから、納税の際に穀物を「升取屋」と呼ばれる升元で納めていたところに由来する」という。(国選択、市の無形民俗文化財になっている)
午後9時30分、集落内の子組、寅組、牛組、申組(各組6名〜8名)の4カ所の升元で宴を開いていた男性たちが、鐘を鳴らしながら公民館に集まってきた。
10時を過ぎた頃、再び門の外に出て、改めての登場。鐘を打ち鳴らし、掛け声とともに棒を振る棒踊りを披露。その後ろからは揃いの着物を着た女性たちが、クバの扇や四竹を持ち、一列になって優雅に舞う。
勇壮な棒踊りに優雅な女性の踊り。それぞれに踊っていたのが、最後は円になり一緒に踊り、五穀豊穣を祈願した。
現在は、穀物で税を納めるということはないが、農業は台風などで大きな被害が出ることがある。豊穣を願う気持ちはいつの世でも同じだ。
会場には地元の人から観光客までたくさん集まり、カメラや?携帯・スマホ等で撮影をしながら、「マストリャー」の踊りに見入っていた。
空に浮かぶ月も「マストリャー」の行事を優しく見守っているようだった。
◇あの話をもう一度
naichar-shima(下地・高千穂出身)
「ミャークフツ講座 形容詞編2」vol.109 2005/10/6
| あかーあか(赤い) | っすぉーっすぉ(白い) |
| っふぉーっふぉ(黒い) | おーおー(青い) |
| だいばん(大きい) | いみーっちゃ(小さい) |
| つぅーつぅ(強い) | よぉーよぉ(弱い) |
| ゆぅーゆぅー(重い) | かずーかず(軽い) |
| すだーす(涼しい) | ぴしーぴし(寒い) |
| ぬふーぬふ(暖かい) | ぴぐる(冷たい) |
| あやすき(怪しい) | ばかすーばかす(可笑しい) |
| ぷからす(うれしい) | うとぅるす(恐ろしい) |
| きちぎ(きれい) | みーちゃぎ(醜い) |
| やまかさ(多い) | いきゃらーぬ(少ない) |
| にうーにう(遅い) | ぴゃーぴゃー(早い) |
| くぱーくぱ(固い) | やぱーやぱ(柔らかい) |
| すぅんざー(うらやましい) | ぱずかすー(恥ずかしい) |
| ばかーばか(若い) | かかみき゜(せわしない) |
| かなすー(愛しい) | やぐみ(尊い、すごい、大変な) |
(例文)
・あかーあかぬ ぱな(赤い鼻)
・っすぉーっすぉ ぬ からず(白い髪)
・っふぉーっふぉ ぬ ぱー(黒い歯)
・だいばん あかーず(大きな蟻)
・うわー ゆぅーゆぅ(あんたは重い)
・うとぅるす みぱな(恐ろしい顔)
・ぴゃーぴゃーてぃ くー(早くおいで)
・かなす ばが っふぁ(愛しい子ども)
ご近所とのつながり
Motoca(平良・下里出身)
保育園で娘を迎えての帰り道は、家までが遠い。歩いたり走ったりがますます活発になってきた2歳児は、寄り道・道草が大好き。
普通に歩けば数分で帰り着けるはずなのに、保育園から出たとたんから家とは逆方向に走りはじめ、道沿いのアパートの階段があれば登りはじめ、石や葉っぱが落ちていれば拾ってママに「はい、どーじょ」。かまくま あす゜きまーり(あちこち歩き回り)、しまいにはお店があれば必ず入っていって、おやつを買わされるハメになる。
まぁ、みなか(お庭)に花が咲いている家があれば「はな、さいたねぇ!」としきりに言い、散歩中の犬に会えば「あ、いぬだ!」と指さし、空に月が出ているのを見て「おちゅきしゃま、こんにちは!」とも言えるようになり、と成長を感じて嬉しくなることも、たくさんあるのだけれど。
成長といえば。娘、2歳になる少し前から自分の名前を言えるようになった。程なく、自分の名前をリズムに乗せて繰り返しながら踊り歩くようになった。お名前、気に入ってくれて嬉しいのだけど、やーんなか(家のなか)のみならず、道を歩きながらも うぷぐい しー(大声で)自分の名前を連呼しながら踊ることもある。最近はフルネームも言える。やがて町内中に名前を覚えられるんじゃないかと、あんな(かーちゃん)はビクビクしている。でも、娘を追いかけながら私も、彼女の名前を連呼していたりするので、んまっふぁ(母娘)揃って、どうしようもない。
その甲斐あって(?)、いつからか、町内に顔を見知っている人、娘の名前を覚えてくださっている人が何人もいる。スーパーの店長、店員さん、コンビニのレジのおばちゃん、保育園の裏の家のおばさま、犬を散歩させているおばあちゃん・・・。会えば、娘の名を呼んで手を振ってくださる。社交家がまである。
半年前までずっと通っていたパン屋さんは残念ながら閉店してしまったが、元オーナーご夫妻とは今もLINEで連絡を取り合い、娘の成長を楽しみにしてくださっている。
そういえばここに引っ越してきたときにいちばん心配だったのは、近隣に知り合いがまったくなかったことだ。大学生活を送った街の近くではあるけれど、当時の友人たちはもう都心部に出たり、里帰りしたりして、近くにはすっかりいない。
その不安はどこへやら、今は自宅を出れば声をかけられる。いや、私じゃなくて、娘のほうにだけれど。きゅうまい、ばんたがっふぁやー(うちの子は)町内を くまかま ぴんぎ まーり(あちらこちら逃げ回り)、いろんな人に声をかけられている。追いかけるのは なんぎ(大変)だけど、おかげで町の人との繋がりができてきたのだと思うと、「まいふかがま(お利口さん)」といって感謝すべきなのかもと思う。ゆうむつ ふふぁ(豊穣をもたらす子ども)って、こういうことかね?
でも。でもさ、たまにはまっすぐおうちに帰らん? 毎度のように帰宅に時間がかかり、夕飯の支度も遅くなってしまうのが、母の悩みどころである。あがえ〜、きゅうぬ ゆーす゜まい(あぁ、今日の夕飯も)、何時になるべきかね〜。
編集後記
松谷初美(下地・高千穂出身)
宮古島市文化協会では、9月29日〜10月1日まで「第12回宮古島市民総合文化祭・一般の部」の展示部門を宮古島市中央公民館で開催しました。部会員や一般市民からの作品が やまかさ(たくさん)集まり、会場はとても華やかでした。
展示以外にも、盆栽の講習会、琉球料理研究家の渡口初美氏の講演会や方言講座、生け花の先生によるデモンストレーション、書道パフォーマンスもあり、好評でした。今年度初の試みの「宮古島Openアトリエ」にも関心が寄せられました。来年もよりよい文化祭を目指して頑張ります。ぜひご参加ください!たんでぃがーたんでぃ〜。
さて、今回のくま・かまぁ、のーしが やたーがらやー?
野原の十五夜マストリャーは脈々と受け継がれていて素晴らしいですね。若い人たちの参加も多くて驚きました。そして観光客の多さにも。いつまでも続いてほしいですね。
あの話をもう一度は、方言講座を取り上げました。繰り返して使う言い方が並んでいます。シンプルですが覚えやすいと思いますので、声に出して読んでみてくださいね。
Motocaさんの、お嬢さんは自分の名前が言えるようになったんですね。自分に名前がある事に気づいた時の感動ったらないはずね。近所の人たちとも仲良くなって まーんてぃ まいふかどー(本当におりこうさんですね)。寄り道、道草は最高の思い出にきっとなりますよ。
貴方の感想もぜひ、お聞かせくださいね。
掲示板への書き込みお待ちしてます!
きゅうまい しまいがみ ゆみふぃーさまい すでぃがふー!
(きょうも 最後まで 読んでくださり ありがとうございました!)
次号は10月19日(木)発行予定です。
きゅうまい ぞう(良い)一日でありますように。 あつかー、またいら!